 |
私は保育者として保育の現場で30年以上働いていました。
保育者には、保育に必要な知識や技術が広く求められます。
例えば、製作的なことも出来なければいけないし、楽譜も読めないと困る、ピアノも弾けないと大変、園児の質問に答えられる科学の知識もないといけないし、絵本だって上手に読める方がいい。このように、オールマイティーな能力が保育者には求められます。
もちろん広く深く、技術や知識があるのが一番なのですがなかなかそれは難しいことです。
でも、技術や知識よりも、「不思議だな〜?」「なんでかなぁ〜?」と、子供と一緒に、本気で考えられる、この視点(好奇心)が本当は重要なんです。
技術や知識は、この好奇心が基になり、広がっていきます。
理想は、オールマイティーな保育者ですが、そんなスーパースターにはなかなかなれるものではありません。私が勤めていた園では、自分の得意・興味のあるものを選び、その担当になりました。
例えば、絵画・造形が得意な先生、歌が得意な先生、絵本に興味のある先生、紙芝居が得意な先生……と1人が1つから2つを選び、担当者になります。担当者はそのことに関する研修等には積極的に出席し、知識技術を深めていくよう努めます。
それを、全職員に伝達講習をして全員が理解し保育していくというシステムを作りました。
さらに、研修等で出会った講師を園に招いて講演会等を企画するのも担当者の役割でした。
例えば「月見」の行事を企画する場合では、その企画に関連する担当者が集まり会議をします。「由来や昔の月見の楽しみ方を調べる」、「関する歌を集め、選ぶ」、「絵本を探し出す」、「月見団子の作り方調べ、作ってみる」など各自で得意なことに関して調べたり、集めたりするわけです。
そして、9月はこの歌を歌い、この絵本を読み、由来を知り、そして団子を作ろう! と職員会議にかけるわけです。
1つの活動を、いろいろな分野から取り組むこのシステムは、保育者にとって自らを向上させ、さらに園全体として質の高い保育が提供できる喜びに満たされ、充実感がありました。
参考にしてみてください。
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
子供のジッーと見つめるあの目、あの声に魅了され、幼児教育にのめりこみ、笑いあり、涙あり、失敗あり…たくさんの喜びと感動の保育者生活35年。
「私の師は子供です」と言い切れるほど、子供から、毎日たくさんのことを教えてもらいました。
この経験を今、現役で頑張っていらっしゃる保育者の皆さんに少しでもお伝えすることができたら嬉しいなと思っています。 |
|
 |
|
 |
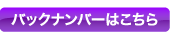 |
|